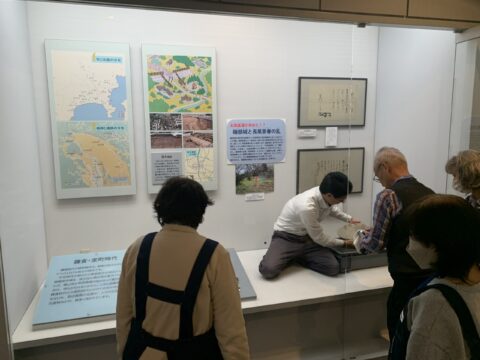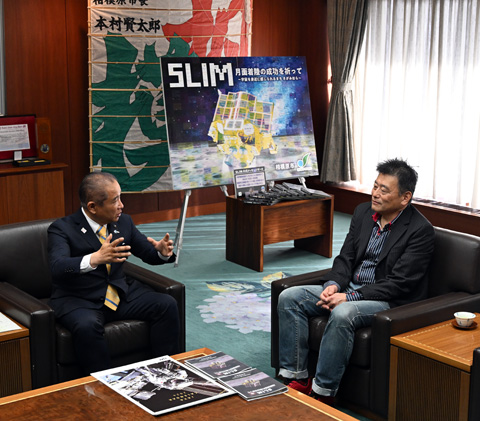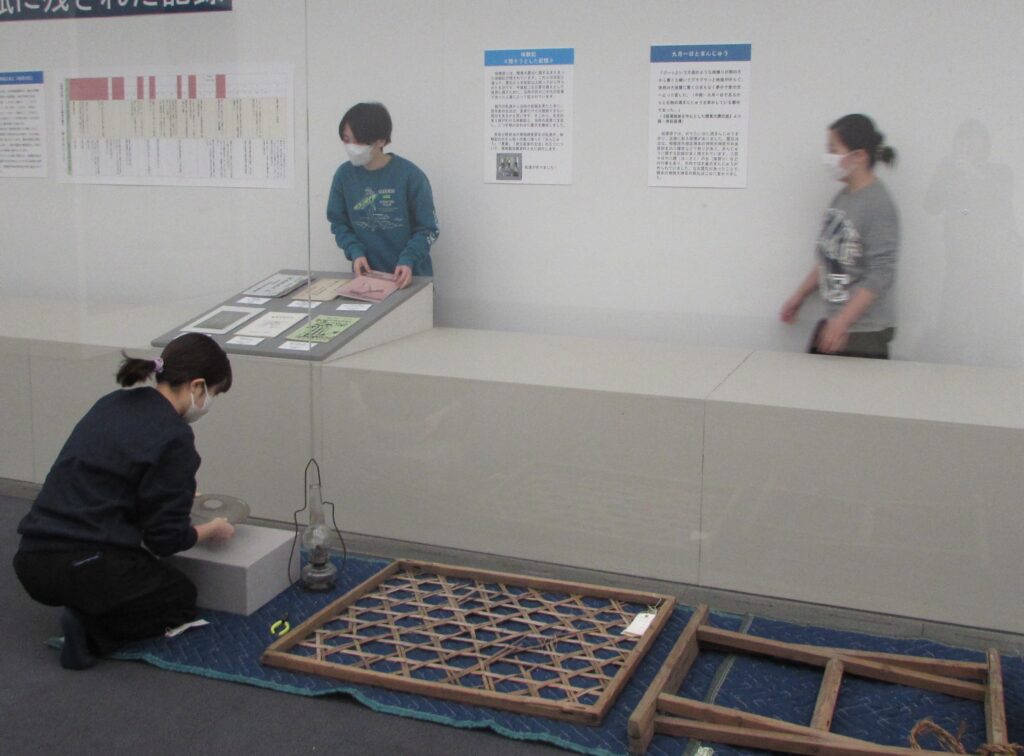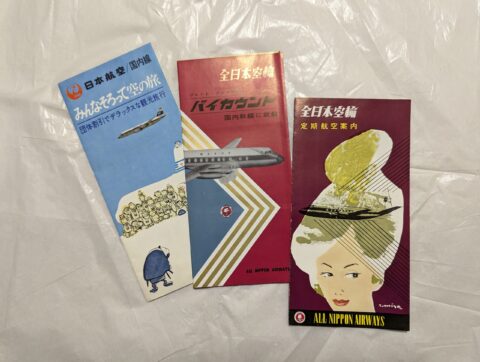新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
相模原市立博物館は昨年12月1日から、館内設備修繕のため、本年2月29日まで休館となっております。
元旦から1月3日までは通常の年始休ですが、4日以降は職員も出勤し、館内のメンテナンスや出前授業、調査など、様々な業務にあたります。
毎年、年末年始はエントランスで十二支ミニ展を開催してきましたが、今年はそんなわけでできません。そこで、このブログ上でのミニ展示といたします。
今年の干支は甲辰(きのえ・たつ)です。十二支はタツ(辰・龍・竜)ということで、トップはこちらです。

追手風喜太郎寄進の「青竜」
幕末の1860年代に活躍し、大関までのぼりつめた市域出身の力士、追手風喜太郎(おいてかぜきたろう)が、地元の神社へ寄進したと伝えられる四神(しじん)のうちの、青竜(せいりゅう)です。相模原市の登録文化財となっています。

美しい木彫
続いて、植物名のちょっとこじつけな、フデリンドウ(筆竜胆)です。博物館周辺の樹林で4月に咲き乱れる、季節を代表する花です。

フデリンドウ(筆竜胆)
竜胆の仲間は根が古くから生薬(しょうやく=漢方薬の原料)として利用されますが、苦みの強さで知られる熊の胆(くまのい=クマの胆のう)よりもさらに苦いということで名づけられたそうです。竜の格の高さがうかがえますね。
そして、こちらはリュウノヒゲ(別名ジャノヒゲ)です。葉が細長く束になって生える様子が、竜の髭(ひげ)にたとえられたのでしょう。写真は、冬に実る果実です。とても美しい青色ですね。

リュウノヒゲ(ジャノヒゲ)の果実
他にも、イネ科のタツノツメガヤやタツノヒゲといった植物も市内で採集されていますが、ちょっとマイナーなので紹介だけにします。
蛇足になりますが、こちらは市内に自生する希少な植物、トウゴクシソバタツナミです。

トウゴクシソバタツナミ(東国紫蘇葉立浪)
「タツ」とつきますが、残念ながらこちらは立浪(たつなみ)で、花の咲く様子が波の立つ様子に見立てられたので、竜とは無関係でした。でもちょっとありがたい雰囲気の写真なので、年の初めの締めとさせていただきます。
(生物担当学芸員)
※相模原市立博物館は、令和6年2月29日までエレベーターの修繕など館内工事のため臨時休館中です。ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いします。休館中のお問い合わせなど、詳しくは博物館ホームページをご覧ください。