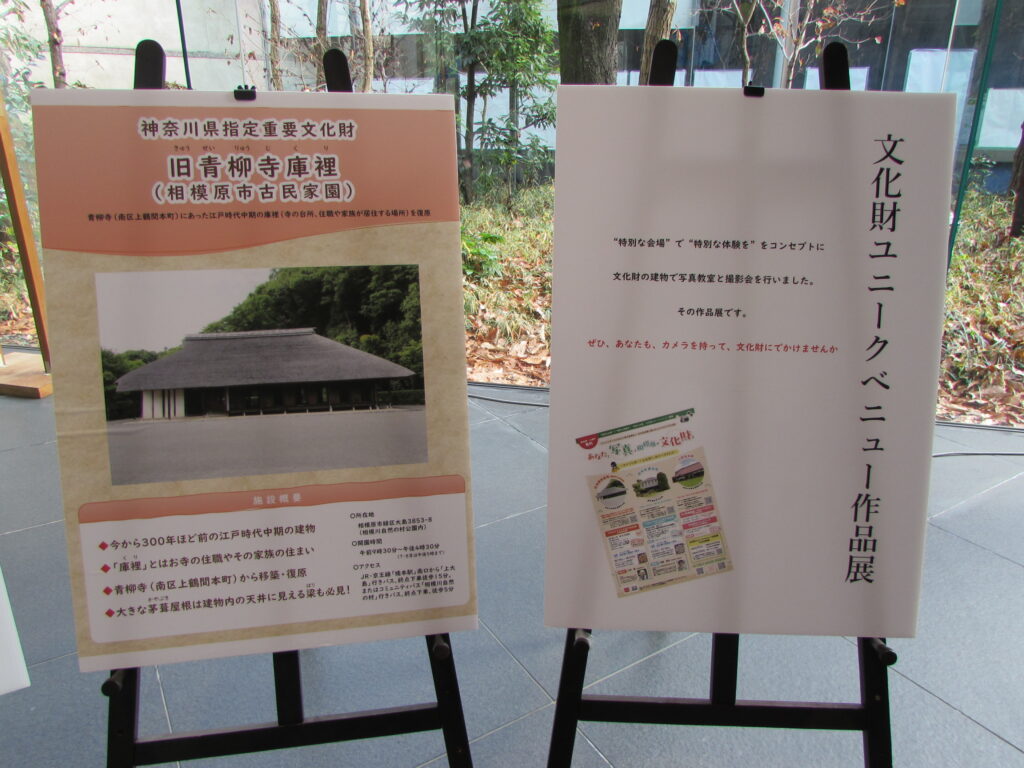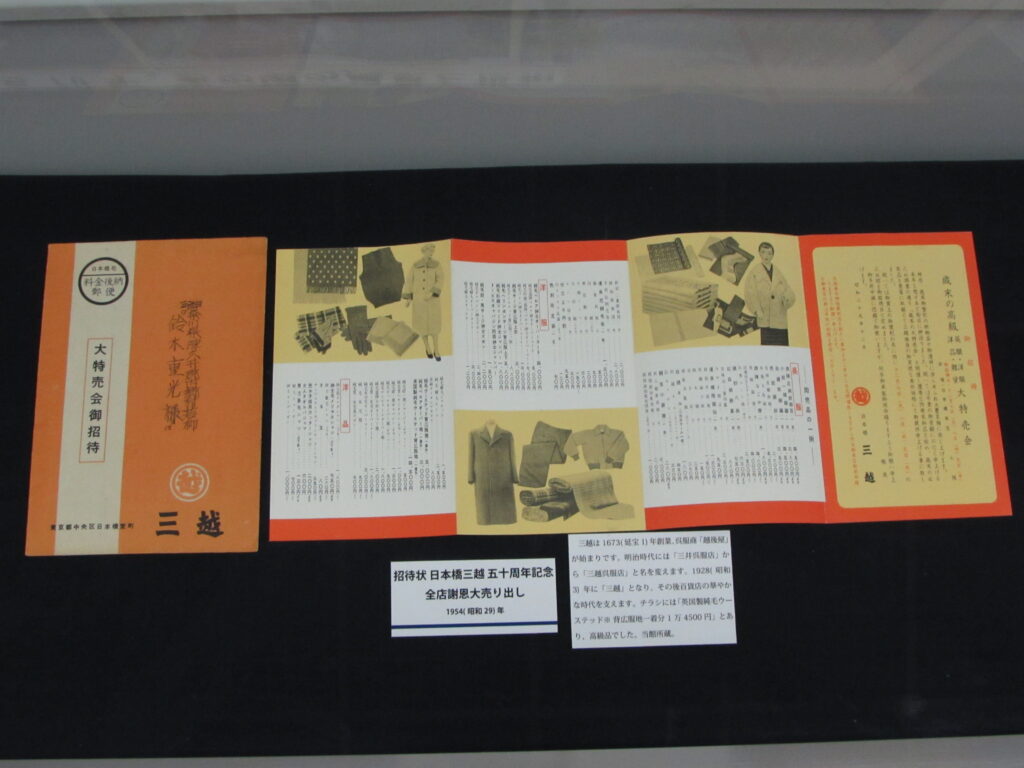1月8日、近隣の公園に行くと、池にトモエガモのオスが泳いでいました。

トモエガモ(オス)
かつては比較的珍しい冬鳥で、飛来すると話題になるような種類でした。しかし近年、県内のあちらこちらへ飛来するようになり、相模原市内の記録も増えています。
それにしても、不思議な顔の模様です。その名のとおり、巴模様(和太鼓に描かれることが多い、勾玉が並んだような日本の伝統的な文様)を連想させますが、色合いといい、その複雑さといい、「なぜこうなったの?」と問いかけたくなるような模様です。

トモエガモ(正面から見たところ)
カモの仲間には、このように複雑で不思議な模様の種類が少なくありません。こちらはシノリガモという海ガモの一種です(相模原では見ることはできません)。

シノリガモ(オス)茨城県の海岸で撮影
筆で白い絵の具を無造作に置いたような模様です。目の少し後方に白くて丸い点があり、見ようによってはこちらが目のようにも見えます。
パンダの目の周りが黒いのは、急所である目を外敵から守るためというのが一つの理由と推測されています(はっきりしたことはわかっていません)。そうだとしたら、タヌキなどの目の周りの模様も同じような理由かもしれません。
カモの仲間にも、愛称「パンダガモ」がいます。和名はミコアイサですが、オスは見事なパンダ模様。

ミコアイサ(オス)
トモエガモやシノリガモ、ミコアイサの模様が目の位置をわかりにくくするためのものかはわかりません。しかし人間にとっては、これらの鳥たちの魅力の一つであることは間違いありません。カモたちの模様や行動を見ながらあれこれ想像を膨らませるのは、冬の楽しみの一つです。
(生物担当学芸員)